ADVERTISEMENT
スポーツウォッチが市場を牽引するなか、クラシカルなエクストラフラットはニッチな存在……かと思われたが、さにあらず。2021年には薄型手巻きの新キャリバーが各社から登場し、けっして時代遅れでないことが証明された。その始祖こそが、1925年にフレデリック・ピゲが開発したCal.21である。にわかに注目を集め始めたCal.21搭載モデルは現在市場から枯渇しつつあるが、江口時計店のオーナーである江口大介氏の協力を得て、興味深いアイテムの数々を撮影することができた。時代を切り開き、極薄ムーブメントを牽引した名機の軌跡を追う。
時代を超え薄型を支えた超ロングセラー機
今ある機械式ムーブメントの基本構造は18世紀のなか頃、フランス人時計師ジャン=アントワーヌ・レピーヌ(Jean-Antoine Lépine)によって考案された。ムーブメントを劇的に薄くした大発明である。薄型キャリバーの元祖を作り上げた彼は巻き上げシステムの延長上に4番車を配置する設計をひとつのスタンダードとした。今でいうレピーヌキャリバーだ。1925年に誕生したフレデリック・ピゲのCal.21は、おそらくこれにならった最初期の腕時計用薄型ムーブメントのひとつだ。直径20.4mm、厚さはわずか1.74mm。誕生から21年にわたり最薄を誇った腕時計用エクストラフラットの始祖は、2番車がセンター、4番車がリューズの巻き芯の延長上、正確には少しずれた8時50分位置にあるレピーヌ構造。当時は(もしかしたら今も)9時位置のスモールセコンドは異質だったことから2針となった。極薄ながら42時間のパワーリザーブを持ち、多くの時計ブランドに供給され、世界恐慌や第2次世界大戦、クォーツショックも生きながらえ、2000年代初頭まで作り続けられた傑作だ。今でもネット上で販売されているCal.21のさまざまなパーツを見ると、地板は香箱部分がギリギリまで掘り下げられ、収める主ゼンマイ量を稼いでいるとわかる。今回の企画に際し、これまでいくつもの時計ブランドと関わり、ヴィンテージウォッチにも造詣が深いNAOYA HIDA & Co.の飛田直哉氏に取材協力を得た。彼のコメントを交えつつCal.21の歴史と魅力を振り返る。彼はCal.21について「パワーリザーブは40時間という資料も見受けられます。振動数は初期では1万8000振動/時で、のちに2万1600振動/時となり、チラネジテンプとスムーステンプもあり、地板とブリッジにロジウムメッキや金メッキがあるなど、Cal.21には多くの仕様違いが存在しています」と語った。
右がオメガのCal.700、左上はベルナード・ゴレイ(Bernard Golay)、左下はギュベリン(Gübelin)の各搭載キャリバー。
上の写真の3つのキャリバーは一例だ。左側の上下ふたつはコート・ド・ジュネーブの向きや香箱の仕上げが異なり、上は17石、下は18石。右側のオメガのCal.700は銅ガルバニックが施され、中央ブリッジの形状もほかとは異なる。オメガのCal.700のようにオリジナルのキャリバー名を付けている例は多い。パテック フィリップのCal.175とCal.177、ロンジンのCal.310、サーチナのCal.20-10など。意外なところではIWCがCal.171の名で、ロレックスもCal.650の名でCal.21を用いていた。また、ブランパンとカルティエはCal.21の名のまま使ったが、ブリッジにはそれぞれのブランド名が入っている。
「ほかにも私が知る限りでは、エベルやユリス・ナルダン、ブレゲ、ショパール、デラノ、コルムなどにCal.21ベースのムーブメントを搭載した例が存在していました。おそらくですが、パテック フィリップなど一部の上位ブランドは別として、多くはフレデリック・ピゲが各ブランドの仕様に合わせた完成品として収めていたと思われます」と飛田氏が語るように、納品先が望む仕上げや装飾に対応できる技術と設備を有していたことがフレデリック・ピゲの強みだ。同時にCal.21はエボーシュとしても供給され、さまざまなバリエーションを生んだ。なかでも別格は、飛田氏も挙げていたパテック フィリップのCal.175と177である。パテック フィリップの公式資料によれば、Cal.175が導入されたのは1963年。テンプはジャイロマックスによるフリースプラングに改められていた。またブリッジの面取りは深く、コート・ド・ジュネーブも幅広で優れた審美性をたたえ、むろんジュネーブ・シールを取得している。これらの改良のためであろうか? オリジナルより0.01mm厚い1.75mm厚となっていた。Cal.177は1977年に登場。Cal.175よりさらに0.02mm厚い1.77mm厚で、各キャリバー名はこの厚さに由来しているようだ。両者最大の違いは振動数である。Cal.175は1万8000振動/時、Cal.177は2万1600振動/時だ。飛田氏が前述したようにCal.21の2万1600振動/時仕様は他社にも存在する。振動数がいつ変わったかがわかる資料は発見できなかったが、Cal.177の導入よりそれほど遠くない以前にハイビート化されたと予測できる。またCal.177にはスケルトン仕様のCal.177 SQUも存在し、2020年にはスロバキアのモルナー・ファブリー(Molnar Fabry)が、Cal.21のニューオールドストックを用いた美しいスケルトンウォッチを製作している。すなわちCal.21は、スケルトナイズできる頑強さもあわせ持っていたことになる。一方で飛田氏は、「これほどバリエーションが多いにもかかわらず、Cal.21にモジュールを搭載していた例を私は知りません。なぜ複雑機構のベースムーブメントとして使われてこなかったのかは謎です」と、疑問を呈する。
Cal.21は2針ムーブメントとして100年近い寿命をまっとうした。しかし誕生初期には注目されていなかったようだ。パテック フィリップが導入したのは1963年。ロレックスは諸説あるが1953年ごろ、カルティエが使いはじめたのも、おそらく1970年代に入ってからだ。なぜ彼らは極薄キャリバーを求めたのか? 1950〜60年代は時計デザインの大きな転換期。特に第2次世界大戦で勝利し、経済的に繁栄したアメリカでは豪華で華やかな時計がもてはやされた。そして丸型、角型だけにとどまらない、さまざまなケースフォルムを各ブランドが試みた。これがCal.21の需要が膨れ上がった要因だ。なぜならムーブメントが薄ければ薄いほど、ケースフォルムの自由度が高まるからだ。1950〜60年代当時、Cal.21に比肩する薄型ムーブメントは存在した。しかし他社に十二分に供給可能な極薄ムーブメントはCal.21しかなかったのだ。
「設計に無理がなく、パワーリザーブも十分で、フレデリック・ピゲは量産と仕様変更にも対応できた。だからCal.21は多用された」というのが飛田氏の見解だが、まったく同意である。1.74mm厚の極薄キャリバーを手にしたデザイナーは創造の翼を自由に広げた。ジェラルド・ジェンタも、そのひとりだ。彼はロレックスのためにCal.21ベースのCal.650を搭載した、飛田氏が「狂気的」と表現するキング・マイダスを創造。またエベルにもCal.21搭載のジェンタデザインがあったことを彼は発見している。
時計デザイン狂乱の時代は長くは続かず、1970年代にCal.21を導入したカルティエは本来の目的であるエレガントなエクストラフラットをかなえるべくタンクやサントスに搭載した。そして1983年、フレデリック・ピゲは当時オメガを率いていたジャン-クロード・ビバー氏とともにブランパンの再興に着手。その頃、テンプの耐衝撃装置がアップデートされたCal.21は、ブランパンのシックス・マスターピースの一翼を担うウルトラスリムを支える存在となった。そんな名機も、ハイビートが当たり前となり、ケースの大型化が進み、2000年代初頭には後進に道を譲ることとなった。とはいえ、これほどの長寿をまっとうしたキャリバーはほかに例がなく、その事実こそがCal.21の設計の優秀さの証しである。
カルティエ Cal.21
薄くフラットな角型ケースには、極薄のCal.21がまさに似合う。
角型ケースにきっちりと収まるCal.21は、テンプの耐衝撃装置が進化した最終形。1980年代製。
カルティエの、そして角型時計の永遠のアイコンであるタンクは、誕生時からルクルト製ムーブメントを用いてきたことは、よく知られている。フランコ・コロニー(Franco Cologni)著の『CARTIER The Tank Watch Timeless Style』に掲載される歴代タンクの多くに“ルクルト製ムーブメント”と明記されるなか、1970年代以降のモデルでは“ラウンド型ムーブメント”となっているケースが増えてきている。おそらくこれらのなかのいくつかがCal.21であったのだろう。これはCal.21搭載のタンクルイカルティエで、製造は1990年代。同じく角型ケースにして腕時計の始祖をルーツとするサントス-デュモンにも、1970年代から90年代までCal.21搭載モデルが存在していた。カルティエはCal.21の晩年を支えたブランドのひとつだった。
パテック フィリップ Cal.175
1970年代製のRef.3523。クッション型ケースの幅は28mm。
18石仕様がベースで、テンプは4つのリムを持つジャイロマックス。
前述のとおり、パテック フィリップはフレデリック・ピゲからCal.21のエボーシュの供給を受けて、自社でチューニングと装飾仕上げを施したCal.175を1963年から、2万1600振動/時仕様のCal.177を1977年から用いてきた。Cal.21ベースのムーブメントは数多いがジュネーブ・シールを取得したのは、これらのふたつだけだ。さまざまなフォルムが模索されていた1960年代に誕生したクッション型のRef.3523はCal.175搭載モデルのひとつで、1970年代まで作られていたほか、Cal.175はクル・ド・パリベゼルで知られるRef.3520やスクエア型のRef.3503などが搭載。Cal.177になってからもRef.3520に継続して使われ、1980年代には地板とブリッジをスケルトナイズし、ハンドエングレービングしたCal.177 SQUが誕生した。
ゼニス Cal.53.5(Cal.2020)
クロックにも似た個性的なフォルムは、1970年代に生まれた。
極薄キャリバーが、ケースのデザインの自由度を高めた典型例だ。
ダイヤルは12時位置にモバード、6時位置にゼニスの名があるダブルネームであるが、ムーブメントのブリッジにはゼニスのロゴだけが刻まれるCal.53.5搭載モデルである。ところが2008年に刊行されたゼニスの歴史をまとめた『Zenith:Swiss Watch Manufacture Since 1865』のムーブメント&キャリバー表には、53.5の名が見つからない。さらに表を詳細に見たところ、2020の名でCal.21と同じサイズと厚みのムーブメントを発見した。サード・パーティ・プロダクトとしてF.ピゲ社の名も記載されている。これが本来のゼニスが供給を受けたCal.21であり、Cal.53.5はモバード向けだったのだろう。同じく表には1万8000振動/時、18石と記載されているが、上の写真のCal.53.5には17石と刻印されている。
Cal.21のあとを追い、レピーヌキャリバー様式を受け継ぐ
1925年当時、懐中時計用も含めればCal.21より薄いムーブメントは複数存在していた。ジャガー・ルクルトは1907年に1.38mm厚のムーブメントを生み出しており、1921年(1925年説もある)にはオーデマ ピゲがさらに薄い1.32mm厚を実現している。フレデリック・ピゲに腕時計用のエクストラフラットキャリバー開発で後塵を拝したオーデマ ピゲは1946年、Cal.21の1.73mm厚をしのぐ1.64mm厚のCal.9MLを完成させた。懐中時計用でレピーヌキャリバーを継承していたからだろうか、Cal.9MLは図らずもCal.21と同じく2番車が中央、4番車が9時位置にある設計となっていた。振動数も初期のCal.21と同じ1万8000振動/時で、パワーリザーブはわずかに及ばぬ36時間。香箱部分の地板を完全にくりぬいた吊り下げ式とすることで、厚みを削っている。各可動パーツに個別のブリッジが与えられたクラシカルで美しい極薄キャリバーは1953年までのあいだ、772個が製作された。そのなかには、本物の金貨に収められたものもあったという。
右はエクストラフラットのお手本。左は装飾的な幅広ベゼルが妖艶な印象である。
右がCal.2003、左がCal.1003。ビーンズ型のひげ持ちなどジュネーブ様式を踏襲する。
Cal.9MLが役目を終えたのは、新たな極薄Cal.2003が完成したからだ。開発にはジャガー・ルクルトとヴァシュロン・コンスタンタンも関与。エボーシュ製造はジャガー・ルクルトが担い、Cal.803をベースとしてまずオーデマ ピゲがCal.2003の名で2年間独占使用し、1955年からヴァシュロン・コンスタンタンがCal.1003の名でラインナップに加えた。オーデマ ピゲが独占使用できたのはCal.9MLの基本設計を流用したからだ。直径20.8mm、厚さ1.64mmのサイズはCal.9MLと同じ。違いはブリッジの数で、剛性を高めるために2〜4番車までをひとつのブリッジとしたため、外観はCal.21に似ることとなった。またレピーヌ構造も共通であり、直径が近いこともあって、Cal.2003とCal.1003はCal.21のフォロワーとも言われる。しかしCal.2003もCal.1003も他社に供給されることはなく、ジャガー・ルクルトのCal.803はあくまでエボーシュであり、自社製品にすら使われることはなかった。Cal.2003は、その名に合わせたように2003年ごろまで使われた。一方のヴァシュロン・コンスタンタンのCal.1003はエボーシュを製造するジャガー・ルクルトが同じグループ傘下であるためか、今もカタログにその名を残し、ヒストリーク・エクストラフラット 1955に搭載されている。
ピアジェのCal.9P。各ブリッジは大きく、薄型ムーブメントを頑強に仕立てていた。ピアジェに名声をもたらした時計史にその名を刻む名機だ。
そのCal.1003が使われはじめた1955年から遅れること2年、ピアジェから極薄手巻きキャリバーが登場する。多くの時計好きが知るCal.9Pである。直径20.5mmというサイズはCal.21やCal.2003、Cal.1003に近く、2mm厚と薄さで劣るのは堅牢な大型ブリッジを採用したからだろう。また1万9800振動/時という当時としてのハイビート機であり、耐久性と携帯精度に優れていた。輪列の配置も先達とは異なり、2番車は中央からオフセットされ、時・分針は筒カナで駆動する設計を採る。しかし4番車に関しては、巻き上げシステムの延長上付近に置いているため、これもまたレピーヌ構造とも呼べ、スモールセコンドをやはり持たない。ゆえにCal.9PもCal.21がモデルであると言われている。Cal.9Pは1980年に量産性を高めるためにブリッジの厚みを増した2.15mm厚のCal.9P2に置き換わり、1998年にはオフセット輪列や大型ブリッジなどを同じとしながら、2万1600振動/時とした2.1mm厚のCal.430Pへと進化した。そしてCal.430Pは、いわゆるリシュモンムーブメントとしてカルティエなどに供給されている。
Cal.21のあとを追い、1950年代に誕生したレピーヌ構造を採る腕時計用の極薄キャリバーは、いずれもCal.21同様に長寿命機となった。ピアジェとブルガリによってケースバックの内側を地板とする新たな構造で極薄時計は新時代に突入した。それらがムーブメントパーツをダイヤルに露わにしているのに対し、レピーヌキャリバーに範を採った薄型の2針が持つソリッドなダイヤルの意匠や装飾に趣向を凝らした工芸的な美に引かれる人は少数派ではないだろう。またキャリバー自体が持つ、クラシカルな構造美や造形美に引きつけられる人も。しかも望めば、そのなかのいくつかは新品で手に入れることができ、良好なアイテムがヴィンテージウォッチで見つかる。今もなお、その魅力を享受できるのだ。
Photographs by Jun Udagawa, Courtesy Eguchi Watch Store






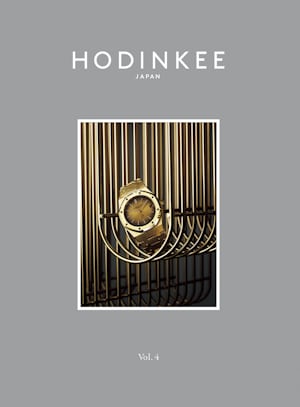















話題の記事
Hands-On パルミジャーニ・フルリエ トリック プティ・セコンドがオリジナルコレクションに新たな息吹を吹き込む
Hands-On アミダ デジトレンド、デジタルドライバーズウォッチで70年代を再現する
The G-SHOCK GMW-B5000D & GM-B2100AD