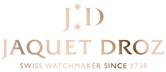スイス高級時計の名門ジャケ・ドローを代表するユニークピースがグラン・セコンドだ。なかでも人気のカンティエームは、従来の43㎜径と39㎜径のケースに新たな41㎜径が登場。その魅力はサイズのバリエーションに留まらず、気品あるエナメル文字盤が個性をより際立たせ、現代のウォッチコノサーの嗜好に応える。
創業者ピエール-ジャケ・ドロー(左)とその息子息子アンリ・ルイ(右)
ジャケ・ドローは、1738年に創業したスイス時計最古のブランドのひとつに挙げられる。その歴史は、生誕300周年を迎える創業者ピエール-ジャケ・ドローの類い稀な先見性と創作への情熱によって始まった。一般的な時計製作に飽き足らず、人間型のオートマタを発明し、美しい装飾を施した音楽機構付き懐中時計を手がけた。そして息子アンリ・ルイとともに、スイス、ロンドンに次ぎ、いち早くジュネーブに時計工房を構え、販路をフランスやイギリス、中国へと拡大したのである。しかし繁栄は19世紀の始まりと共にその幕を一旦閉じることに。やがて21世紀を迎え、スウォッチ グループに加わり再興を遂げたのだ。
現在ラ・ショー・ド・フォンにある本社アトリエでは、時計製造に加え、細密画や彫金、パイヨンなど伝統的な装飾技法を育み、オートマタの開発や歴史的なタイムピースの復元作業も続けられている。中でもエナメル文字盤の自社製造は、スイス高級時計ブランドでも限られている。そこではアートとデザインと技術の融合を目指し、時代を超越したクラフトマンシップが注がれ、まさにアトリエと呼ぶにふさわしい。
焼成されるエナメル文字盤の様子。
ラ・ショー・ド・フォンの本社アトリエ。
2002年にジャケ・ドローは深い眠りから目覚めた。その新たな飛躍のシンボルとして発表されたモデルがグラン・セコンドだ。18世紀後半ジャケ・ドローは中国の顧客に向け、数多くの懐中時計を製作。1784年頃には、中国において運を呼ぶラッキーナンバーである8をモチーフに、アワーダイヤルとセコンドダイヤルの二つの円が重なる斬新なデザインを発表した。
グラン・セコンドは、その革新的なスタイルにインスピレーションを得て、腕時計として現代に甦らせたのである。シンプルでありながら、伝統に培われたクラシックと先進技術のモダニティを併せもち、アヴァンギャルドな美学が漂う。そしてブランドのアイコンとしてその再興と足並みを揃え、ベーシックな3針からハイエンドのコンプリケーションまで多彩なバリエーションを揃えるフルコレクションへと成長を遂げた。存在感あるフェイスは、幸運の数字を表すと同時に、無限大を意味する記号を思わせ、まさに無限の可能性を予感させるのだ。
グラン・セコンドは、ブランドの伝統を受け継ぎつつ、決してそこに留まることはない。グラン・セコンド カンティエームこそその象徴だろう。オフセンターのふたつの円からなるデザインを崩すことなく、セコンドカウンターにポインターデイトを併設する。
左からグラン・セコンド・カンティエーム39mm、41mm、そして43mmモデル。
そして新作では、従来の43㎜径と39㎜径のケースサイズに新たに41㎜径を加えた。それもただケース径を拡張するのでなく、わずかだが厚さを薄く抑え、ラグ形状も改良し、より心地良いフィット感が得られる。サイズに合わせてケース全体を見直すことで、美しい調和を実現したのだ。コレクションの熟成は3つのサイズを比べてみれば一目瞭然だろう。それぞれ異なる個性を醸し出し、最適な1本が選べるのである。
ダークブルーのエナメル独自の素材感に、レッドゴールドのメタルリングがシックに映える。
シンプルでありながらも文字盤に独自の気品と美しさを演出するのが“高温焼成”エナメルだ。金属の表面にガラス質の釉薬を焼き付け、被膜を作ることで、独特な美しさと光沢を生み、経年劣化も防ぐ。とくに高温での焼成には高い技術とノウハウが求められ、ジャケ・ドローは18世紀以来この“高温焼成”エナメルの最新の技術開発を自社で手がけている。ダークブルーの文字盤には精細な粒子感のある艶が浮かび、いつまでも見惚れてしまう。
ケース厚は8.48㎜になり、他サイズに比べて1㎜弱薄くなった。さらにラグは短くするとともに、下向きに改良し、装着感も優れる。
ローターをオープンタイプに変更し、シリコン製ヒゲゼンマイを採用する精緻な動きがより見やすくなった。
さらに新たな試みとして加えられたのが、ポインターデイトのメタルリングだ。視認性を向上し、ケースや指針と同色にすることで一体感が際立つ。一方でアワーやセコンドトラックの線を細く控えめにすることで、優雅な洗練も感じさせるのだ。内蔵するムーブメントは、基本スペックは変わらないものの、ローター形状を変更。さらにケースバックのサファイアクリスタルをドーム状にすることでケース厚を抑える。これもクラシックの伝統が息づくスタイルだ。
懐中時計を範とするデザインから、ジャケ・ドローにはまずフォーマルなコーディネートが思い浮かぶ。正統的なドレスコードにも最適だろう。だが魅力はそれだけではない。オフセンターのオリジナリティ溢れるデザインは、アクティブな印象をもたらし、レザージャケットのようなカジュアルにも向く。それでいて大人の品格を醸し出すのも魅力だ。ほど良いサイズ感は、ドレッシーなスーツやジャケットにも合うと共に、文字盤やケースとカラーコーディネートしたレザーストラップからはモダニティが漂い、袖元にスタイリッシュを添えるのだ。コレクションには、SSケースのバリエーションも揃える。そのラインナップからもエレガントからスポーティまでこなすフレキシビリティが伝わってくるだろう。
グラン・セコンド カンティエーム アイボリーエナメル
217万円(税抜)
自動巻きCal.Jaquet Droz 2660Q2。68時間パワーリザーブ。18K RGケース、直径41mm × 12.1mm。手縫いのライトブラウンアリゲーターストラップ。3気圧(30m)防水。
グラン・セコンド カンティエーム ダークブルーエナメル
217万円(税抜)
自動巻きCal.Jaquet Droz 2660Q2。68時間パワーリザーブ。18K RGケース、直径41mm × 12.1mm。手縫いのダークブルーアリゲーターストラップ。3気圧(30m)防水。
グラン・セコンド カンティエーム バーガンディーエナメル
217万円(税抜)
自動巻きCal.Jaquet Droz 2660Q2。68時間パワーリザーブ。18K RGケース、直径41mm × 12.1mm。手縫いのバーガンディーアリゲーターストラップ。3気圧(30m)防水。
グラン・セコンド カンティエーム アントラサイトエナメル
217万円(税抜)
自動巻きCal.Jaquet Droz 2660Q2。68時間パワーリザーブ。18K RGケース、直径41mm × 12.1mm。手縫いのブラウンアリゲーターストラップ。3気圧(30m)防水。
グラン・セコンド カンティエーム マットブラック
103万円(税抜)
自動巻きCal.Jaquet Droz 2660Q2。68時間パワーリザーブ。ステンレススティールケース、直径41mm × 12.1mm。手縫いのブラックカーフストラップ。3気圧(30m)防水。
グラン・セコンド カンティエーム チタニウムグレー
103万円(税抜)
自動巻きCal.Jaquet Droz 2660Q2。68時間パワーリザーブ。ステンレススティールケース、直径41mm × 12.1mm。手縫いのダークブルーカーフストラップ。3気圧(30m)防水。
グラン・セコンド カンティエーム シルバー
103万円(税抜)
自動巻きCal.Jaquet Droz 2660Q2。68時間パワーリザーブ。ステンレススティールケース、直径41mm × 12.1mm。手縫いのダークグレーカーフストラップ。3気圧(30m)防水。
Photographs:Yoshinori Eto, Words:Mitsuru Shibata