ADVERTISEMENT
本記事は、2021年7月に発売されたHODINKEE Magazine Japan Edition Vol.2に掲載されたものであり、記載している価格は2021年7月当時のものです。HODINKEE Magazine Japan Editionの定期購読はこちらからご登録いただけます。
ラグジュアリーコングロマリットが展開するグローバルブランドとは異なり、小規模ながらも独自のこだわりを反映した時計作りを貫くインディペンデントブランドが、市場で存在感を強めている。彼らを支持するのは、目の肥えた時計愛好家たちだ。インディペンデントブランドは古くから存在しており、決して珍しいものではない。では、なぜ今彼らが注目を集めるのか。人々の心に響く時計とは何かということ、そして、時計ブランドの未来が見えてきた。
インディペンデントブランドの黎明期
高級商材としての機械式時計が復権を遂げ、1990年代の終わりごろから市場を席巻した大規模な“業界再編”を経て、スイスを代表する多くの時計ブランドは、リシュモングループ、LVMHグループ、ケリング(旧PPR)など、いわゆるラグジュアリーコングロマリットの傘下企業となった。時計製造業のみを基盤とする企業体としては、最大手のスウォッチグループがこれに続く。この時代の“インディペンデント”とは、こうした企業体に属さない独立資本の時計ブランドを指す。ロレックス、パテック フィリップ、オーデマ ピゲなども、この定義に従うならばれっきとしたインディペンデントブランドの範疇(はんちゅう)だといえる。
一方、グループ内企業間でのプラットフォーム共有化に伴い、この時代の機械式時計は画一化が一気に進んだ。こうした状況のなかで登場したのが、どのグループにも属さずに個人で時計製造を行う作家たちだ。彼らはのちに独立時計師=インディペンデントウォッチメーカーと呼ばれるようになり、1985年に結成された独立時計師アカデミー(AHCI)の存在が広く知られるようになるにつれ、インディペンデント=独立時計師という認識が一般化していった。しかし、独立時計師自身のブランド化が加速すると、個人作家の規模を超えるレベルにまで生産規模を拡大していく例も見られるようになる。
フランク・ミュラー氏はひとりの独立時計師としてキャリアをスタートさせたが、傘下にウォッチランドを擁する規模にまで発展。現在のフランクミュラーは全体で4万〜5万本の年産数を数えるまでに巨大化しており、もはやこれをインディペンデントと見なす人は少ないだろう。現代的な解釈におけるインディペンデントとは、作り手の個性を反映しつつも、生産体制を個人の技量に依存せず、かつあまり大きくない生産規模にとどまる小規模ブランドと定義できるだろう。観念上では資本の独立性よりも、ほかにはない個性とあまり大きくない生産規模こそが、インディペンデントの要件とされているようだ。
F.P. ジュルヌ トゥールビヨン・スヴラン 3162万5000円。
1985年ごろからパリのサンジェルマン・デ・プレで独立時計師としての活動を始めたフランソワ-ポール・ジュルヌ氏は、88年から活動の拠点をスイスに移した。工房設備を充実させて、正式にモントル・ジュルヌSAを設立したのは99年のことである。現在のF.P.ジュルヌはジュネーブの本社工房のほかに、ダイヤル工房のカドラニエ・ジュネーブとケース工房のボワティエ・ジュネーブを擁し、生産のほぼすべてを自社内で賄えるまでに成長を遂げている。ジュルヌが有する工房は、ダイヤルサプライヤー、ケースサプライヤーとしても業界内の高い評価を得ており、名だたるビッグメゾンへの供給も行っているが、その半面、F.P.ジュルヌ名での時計の生産数は年間約850本程度で推移している。ジュルヌ氏自身の言葉に従うならば、これくらいの数量が「自分ひとりで隅々まで目が行き届く上限」なのだという。
最先端テクノロジーを駆使したエクストリームウォッチが多くの愛好家の心を捉える。RM 65-01はリシャール・ミルの技術とイノベーションの集大成として2020年に発表された。リシャール・ミル RM 65-01 オートマティックスプリットセコンドクロノグラフ 3586万円。Courtesy Richard Mille
希少性という点で言えば、2001年にブランドをローンチさせたリシャール・ミルも入手困難な時計の筆頭だ。正式な生産数を公表していないが、現在は年産5000本程度のキャパシティをもっているようだ。希代のコンセプターとして名をはせるリシャール・ミルだが、当初は共同創業者であるドミニク・ゲナが擁するゲナ・モントレ・ヴァルジンを拠点としつつ、数々のサプライヤーとの共同開発によって製造を賄う“ファブレスマニュファクチュール(ムーブメントの設計は自社で、製造は他社に委託するという形態)”の筆頭だった。
余談だが、“2010年問題”と呼ばれたETAのエボーシュ供給問題に着地点が見えなかった2000年代前半は、自前の製造設備をもたずに自社開発を行うファブレスマニュファクチュールが多かった。こうした業態は10年ほどで下火となり、独自の開発力をもったブランドの多くは“リアルマニュファクチュール”を指向するようになり、リシャール・ミルもまたその道を歩むことになった。現在のリシャール・ミルは本社工房であるオロメトリーを筆頭に、難切削材の加工を可能とするプロアートⅠ、R&Dとジェムセッティングなどを行うプロアートⅡのほか、ノース・シン・プライ・テクノロジーと共同で設立したカーボンTPT®などの生産設備まで擁するようになった。とびきりのプライスタグと引き替えに、独特な着眼点と先進素材を駆使して作られるプロダクトは、インディペンデントであるからこそ可能な“創造の自由”にあふれているのだ。
SNS が加速させた新時代の幕開け
1990年代末から2000年代初頭にかけて、自らのブランドローンチを成功させたF.P.ジュルヌとリシャール・ミル。一方は希代の独立時計師として、もう片ほうはブシュロンやモーブッサンに携わったコンセプターとしてともに頭角を現し始めた1980〜90年代は、機械式時計にとって冬の時代だった。それが理由なのかはわからないが、両者ともに自身のインディペンデントブランドの確立に成功すると、貪欲に生産設備の充実に努めた。彼らの時計はマニュファクチュールであるがゆえに希少価値を高め、わずか十数年の間に製造された時計のほぼすべてが、希少なヴィンテージウォッチと同等以上の扱いを受け、オークションシーンをにぎわす存在となっている。
2015年11月に発表されたチャペックのケ・デ・ベルク。クラウドファンディングを通じて資金調達を行うスタイルは低価格帯の時計に限られていたが、チャペックの成功により、高級時計でも有用であることを示した。Courtesy Czapek
一方、時代がひと回りして機械式時計を作り出す環境が爛熟(らんじゅく)期を迎えた2010年代以降は、新しい形態のインディペンデントブランドも登場してくる。クラウドファンディングで出資者を募ったチャペックなどはその筆頭だろう。パテック フィリップの前身として知られているパテック・チャペックに名を残すポーランド人時計師、フランソワ・チャペック。高級時計の世界に造詣の深い起業家のハリー・グール氏、ザビエル・デ・ロックモーレル氏、時計師のセバスティアン・フォロニエ氏の3人が集まって、その名を復活させようという試みは2013年から始まった。インターネットとSNSを通じて、世界中の時計愛好家に対して発信されたブランド復興の呼びかけは、2015〜16年にかけて100名を超える賛同者を得て、ファーストモデル「ケ・デ・ベルク」の開発に向けて動きだした。大資本や特定のパトロンが持つ財力に頼ることなく、100名を超える時計愛好家自身がブランドオーナーとなったのである。
新生チャペックが採用した開発方法は、かつてのファブレスマニュファクチュールと同様だ。19世紀に作られたオリジナルのチャペック「No.3430」(もちろん懐中時計)から、ツインバレルの配置やダイヤルレイアウトを逆算したCal.SXH1を新規設計。製造のパートナーとなったのはジャン=フランソワ・モジョン氏の率いるクロノードで、第2作めとなったトゥールビヨンのCal.SXH2も同様である。超ハイビートの自動巻きクロノグラフであるCal.SXH3はヴォーシェ・マニュファクチュール・フルリエのエボーシュを再設計した。特殊なXOスティールを用いるケースは高品質なSSの生産に特化したモンタンシュトール製。特徴的なフルール・ド・リスの時分針やダイヤルなども名だたるサプライヤーから供給を受けている。こうした協力サプライヤーのネットワーク化を、彼らは“水平統合システム”と呼んでいる。
本当の意味でチャペックの転機となったのは2020年だろう。この年に発表されたアンタークティックは同社初のブレスレットウォッチであり、デイリーラグジュアリーの開発を強く求めた顧客たち(その一部はブランドオーナーでもある)の声に応えたものだ。往年のブレゲよろしく、スースクリプション(手付として先に代金を半分支払う注文販売のこと)形式でインターネット受注を行ったところ、発表から数週間でファーストロットは予約完売。その後の開発経緯はSNSを通じて発信され、完成を待つオーナーたちはリアルタイムで見ることができた。もっとも、こうしたSNSを駆使した顧客とのコミュニケーションに先鞭を付けたのは、MB&Fのマキシミリアン・ブッサーだろう。
いわゆるミドルレンジに属する価格帯のインディペンデントブランドでは、インターネットを利用したD2C(消費者直接取引)の形式を採ることで大きな成果を挙げる例が多くなってきた。かつてオーデマ ピゲのデザインディレクターだったオクタビオ・ガルシア氏のゴリラ、時計師のヨハン・ストーニ氏とデザイナーのバスティアン・ヴィリオメネ氏が立ち上げたランディブルーなどはその好例で、エンドユーザーとのコミュニケーションと物流に関わる中間コストを開発に振り向けることで、ミドルレンジとは思えない優れた質感を実現している。
オフィオン 786 ヴェロス 63万9000円。
スペインのマドリードに本拠地を置くオフィオンも、3000ユーロ前後の価格帯ながら、時計愛好家から支持を集めるインディペンデントブランドだ。ブランドの立ち上げは2014年。インターネット上で開発時のデザインCGを公開したうえでプレオーダーを募るという形式で、ファーストモデルのOPH 960を15年に発表。19年に現在の最新作となるOPH 786 ヴェロスが登場している。
オフィオンのInstagramアカウントの画面。今や多くの時計ブランドがエンドユーザーとダイレクトにコミュニケーションを取っている。時計ブランドとの初めての接点がInstagramという人も少なくないのではないだろうか。
ケースバックに刻まれた“70% Swiss 30% German”のとおり、ツインバレルと約120時間のパワーリザーブを備えるムーブメントは、先ごろソプロードの傘下となった旧テクノタイム製。往年のブレゲの時計を模したような受けの造形は、オフィオンからの意向に沿ってカスタマイズされたものだ。ムーブメント表面に施された独特なテクスチャーは18世紀の懐中時計を連想させる。CNCによるギヨシェを刻んだダイヤルはドイツのカドール。ヴェロスの名の由来でもある矢をかたどった針はスイスのエスティマ。ティアドロップラグを持つケースはカリ・ヴティライネンが所有するヴティライネン&カティンが手がける。なおヴティライネンはダイヤルサプライヤーのコンブレマインも所有しており、こちらはのちに述べるキクチナカガワも使用している。
F.P.ジュルヌやカリ・ヴティライネンのような、優れたインディペンデントブランド自身が自社製品のためにサプライヤーを所有し、そのキャパシティを外販に振り分けたことも、ランディブルーやオフィオンのような小規模ブランドが、小回りの利いた製品開発を行えるようになったバックボーンのひとつだろう。FacebookやInstagramに象徴されるSNSの普及はデジタルネイティブの顧客層とインディペンデントブランドたちを密接に結びつけただけでなく、インディペンデントブランド同士の相互ネットワークも密なものとしているようだ。
世界が注目する日本のインディペンデント
NAOYA HIDA & Co. NH Type 1C 203万5000円。
キクチナカガワ MURAKUMO 239万8000円。
日本におけるインディペンデントブランドの存在が意識され始めたのは、独立時計師として知られる菊野昌宏氏や浅岡肇氏がAHCIに名を連ねて以降だろう。セイコー、シチズンといった独立資本の巨大ブランドを抱える日本では、インディペンデント=個人作家のみが知られてきた。しかし近年では、プロダクトマネージャー的な見地から、ウォッチメイキングをコントロールするインディペンデントブランドも台頭してきている。2018年にNAOYA HIDA & Co.と名付けた自社ブランドを立ち上げ、翌19年にローンチモデルをリリースした飛田直哉氏。同じく18年にデビューを飾ったキクチナカガワがその両雄だ。
1990年代から高級時計を扱う複数の外資系専門商社でセールスやマーケティングを担当し、日本市場向けの製品開発やプロダクトマネジメントを手がけてきた飛田氏は、ヴィンテージウォッチにも造詣が深く、卓抜した審美眼を持つ人物として業界ではよく知られている。そんな飛田氏が自ら時計ブランドを立ち上げる原動力となったものは、ある種の諦めだったようだ。
飛田氏いわく、自分が理想とする時計をスイスのブランドは作ってくれず、ヴィンテージの世界にも理想の一本は見つけられなかったという。そうしたタイミングで菊野氏や浅岡氏が登場し、日本人時計師でも高級時計の世界で活躍できる道を示した。もっと現実的な面でいえば、ある産業見本市で見かけた碌々(ろくろく)産業の微細加工機が大きな転機となったという。工作精度をミクロン単位でコントロールできるCNC制御の研削機械に出合ったことで、可能性が開けたと彼は語る。また、設計と組み立てを担当する藤田耕介氏は、2015年ごろから試作を開始したサンプルの出来映えが思った以上によかったことで、大きな手応えを得たという。
飛田氏が最初に作りたいと願った理想の時計とは、直径37mmの小ぶりなサイズで素材に904Lステンレススティールを用いたケースを備え、ケースにぴったりと収まるムーブメントとヴィンテージの味わいだ。現代的な加工技術と職人の手作業を組み合わせることで、誰も見たことのないような時計を作る。そうした飛田氏の願いはデビューから3シーズンめを迎えて、ほぼ理想的なリアクションとともに愛好家に受け入れられたようだ。新作発表と同時に受注を開始した2021年の生産予定分は、すでに予約完売。年産40本という極少のキャパシティを考えても飛田氏の時計は、いま最も入手困難なレアピースのひとつとなっている。
碌々産業の微細加工機を駆使して作られるNH Type 1Cのケースは、プロトタイプの1Aから細かなバランス調整を重ねて完成されたもの。ダイヤルは洗浄と下地研磨を徹底することで、しっとりとした質感を得ている。
これほどまでに愛好家を熱狂させる要因は、飛田氏の見識に由来する卓抜したバランス感覚だろう。そしてそれは1作ごとにすごみを増している。碌々産業の微細加工機を用いて、磨きなしでケース加工を仕上げまでもっていったのが、18年にプロトタイプとして製作されたNHType 1A。初期製品版となったNH Type 1Bではラグを細く絞り、ミドルケースのボリュームを増加。さらに適切な磨きを加えることで、腕へのあたりをソフトにしている。掲載したNH Type 1Cは、1Bからラグの両肩を0.5mmほど削り落とし、ロゴの位置を0.37mmほど上方に移動させた。さらに製造の途中からダイヤルの製法を見直し、下処理となる洗浄と鏡面加工を徹底したうえで、ビーズブラストを極低圧で吹き付けるように変更された。ジャーマンシルバー製のダイヤル表面はノントリートメントで仕上げられるが、以前よりもしっとりとした白みが増していると感じる。ブランドロゴは微細加工機による切削だが、インデックスは3人めのパートナーである彫金師による手彫り。そこに流し込まれたカシュー(人工漆)のしっとりと濡れたようなつや感がなんとも美しい。
飛田氏によれば、今後生産を予定している時計の約70%は海外からの受注だという。これもSNSを駆使したPRコミュニケーションの恩恵だが、そもそもSNSがなかったら、時計ブランドを立ち上げるという構想そのものが頓挫していたかもしれないとも語っている。スタッフ間の連携という点でも、新しいコミュニケーションツールがもたらした恩恵は大きい。
インディペンデントブランドが大きな市場評価を得ている現状について、「多くのユーザーが作り手の顔が見える時計を探していたのかもしれない」としながらも、飛田氏は決して楽観的な展望をもってはいない。かつて日本にもあった独立時計師ブームが長続きしなかったことを考えても、手放しでは喜べないとも語る。
一時的に大きな成功を収めても、それを継続できずに信用を失い、消えていったインディペンデントは数多い。端的な例を挙げるなら、適切なタイミングで納品することすらかなわない個人作家たちはまだ多いのだ。年産40本というキャパシティはいかにも小さいと感じる向きも多いだろう。しかし、確実に生産できる上限を見極め、それを確実にこなす飛田氏の堅実な姿勢の裏には、注目されながらも消えていった先達たちを見続けてきた、飛田氏のシニカルな視点があるのかもしれない。
Courtesy Kikuchi Nakagawa
MURAKUMOが搭載するムーブメントは、ヴォーシェ・マニュファクチュール・フルリエ製のマイクロローター自動巻きがベース。決してトルクの大きな機械ではないが、時分針には重厚な造形が与えられている。ヴティライネン傘下のコンブレマインで作られるダイヤルは、極めて立体的なデカルク(印字)をもっている。
飛田氏がブランドを立ち上げた2018年には、日本にもうひとつのインディペンデントブランドが誕生している。時計理論家の菊池悠介氏と、時計師の中川友就氏が起ち上げたキクチナカガワである。菊池氏は東京大学工学部建築学科を卒業し、就職していた会社を辞して渡仏。パリ時計学校に入学する。帰国後、個人製作のためにChronomètreを創業するが、これが18年に発展的解消を遂げ、中川氏と共同でキクチナカガワを立ち上げることとなった。時計師の中川氏は、シチズンマイクロからシチズン時計へと移籍し、製品開発にも携わった。シチズンを去ったあとは、16年から浅岡肇氏の東京時計精密で腕を振るう一方、菊池氏とともに自社ブランド設立の準備に奔走した。そんな彼らの初作となったのがMURAKUMOである。
直径36.8mmのSSケースに、ヴォーシェ・マニュファクチュール・フルリエ製のマイクロローター自動巻き。スペックだけを見れば、MURAKUMOにユニークな要素は乏しい。しかし、このオーソドックスな構成の時計が、世界の時計愛好家の琴線に触れたのだ。理由のひとつは、菊池氏の時計理論から導き出された緊張感のある造形美。そして刀鍛冶の経験をもつ中川氏の、過剰なまでのブラックポリッシュだ。鏡面仕上げのなかでも最高峰とされるブラックポリッシュは、面のゆがみが極端に少ないことから研磨面が真っ黒に見える。通常はネジの頭や面取りなどに施すのだが、中川氏は外装部品のすべてにこれを施すのである。MURAKUMOはケースのプロポーションも独特だ。それが最も顕著なのは36.8mmのケース径に対してはやや広すぎる22mmのラグ幅。これと同様のバランスをもつ時計といえば、パテック フィリップの名作、Ref.96が思い当たる。MURAKUMOを見たユーザーが最初に感じるであろう“和製カラトラバ”の印象は巧妙に仕掛けられたものなのだ。
常にペアで活動していると思われがちなキクチナカガワだが、実のところふたりの活動拠点は東西に分かれている。最近、子息が誕生したばかりの菊池氏は神戸を拠点としているが、中川氏の工房兼自宅は東京郊外にある。顧客とのコミュニケーションツールとしてInstagramの利便性を強調する彼らだが、SNSがなければ、そもそもふたりの連携もままならない。ヴォーシェ・マニュファクチュール・フルリエやダイヤルを製造するコンブレマインといった優れたサプライヤーとの連携にもSNSツールは有用だろう。しかし、彼らの時計がもつ本当のすごみは、インターネットの画面を通してでは決して伝わらないとも言える。あたかも研ぎ澄まされた日本刀のような存在感は、実機を見ることでしか体感できないのである。
時代を超えて人々の心を捉える時計の本質
情熱をもった時計職人や愛好家たちは自らが理想とする時計を手がけるべく立ち上がった。そして閉鎖的だった業界に新風をもたらすとともに、たとえ小規模でも多様化した価値観、ニーズにフィットする時計が受け入れられることを示した。
(左)ミン 17.06、(右)クロノトウキョウ クロノグラフ。
結果、多くの時計ブランドが誕生しており、魅力的なブランドはけっして少なくない。例えば、ミン。2017年にミン・ティエン氏が中心となり、マレーシアで誕生したブランドだ。デビューモデルの17.01は立体的なマルチレイヤー構造をもつギヨシェ彫りダイヤルを備え、ムーブメントこそありふれたセリタのエボーシュだが、250時間のテストにより5姿勢で調整された高品質なものを採用。現在は、シュワルツ・エティエンヌの子会社であるラ・ディビジョン・デュ・タンが組み立てと品質管理を行う。デビューから2年後の19年には、時計界のアカデミー賞と称されるGPHGにおいて、17.01のバリエーションである17.06がオロロジカル・レベレーション賞を受賞。1250スイスフラン(約16万円。デビューモデルの17.01は、発売当時900ドル/約10万円だった)という手ごろな価格ながら、確かな評価を獲得している。
また、独立時計師である浅岡肇氏がデザイン・設計するクロノトウキョウも目を見張るような魅力を備えたブランドのひとつだ。浅岡氏が自分自身でつける時計が欲しいという理由から誕生した時計ブランドであり、彼が独立時計師としてすべての工程を手がける作品と同じデザインDNAをもつ時計を手ごろな価格で提供。デザインは浅岡氏が、製造は彼が代表を務める東京時計精密が担う。特にダイヤルの作り込みには手をかけており、膨らみのあるボンベダイヤルにはミラーフィニッシュと呼ばれるつやのある塗装が施されるほか、立体的なドットインデックス、インダイヤル外周(金属光沢のあるエッジ部分)のダイヤカットなど、かつてのヴィンテージウォッチに見られた優れたディテールを現代の高度な加工技術で表現し、卓越した質感を生み出した。ミンもクロノトウキョウもインターネットを通じてオンラインで販売されるが、売れ行きは順調。この事実からも、作り手のこだわりを反映した時計が目の肥えた愛好家たちから高い評価を得ている状況がうかがえる。
アトリエ・デ・クロノメトリ/スペインのバルセロナに誕生。CNCなど現代的な工作機械を使用しない時計づくりが信条。完全受注生産で、同一デザインでの再注文は受けないというポリシーを貫く。AdC #7。605万円。Courtesy Atelier De Chronometrie
フェノメン/カーデザイナー出身のアレクサンドル・メイエー氏が2017年に設立したメイド・イン・フランスの新鋭。ファーストモデルのPH-01はドライバーズウォッチの新しい形を示した。PH-01 フルチタニウム。830万5000円。Courtesy Phenomen
ペテルマン・ベダ/2017年にエル・ペテルマン氏とフロリアン・ベダ氏がスイスに創設。プロトタイプの開発を経て、2019年にデッドビードセコンド機構を備えるRef.1967を完成させた。Ref.1967。5万9800スイスフラン。Courtesy Petermann Bédat
インディペンデントブランドの台頭がもたらしたのは決してメリットばかりではない。小規模でもビジネスの見通しが立てやすくなった結果、クオリティよりもデザイン的な目新しさや安価なだけの有象無象の時計を多く生み出していることも否定できない事実だろう。だが同時に、価格を問わず、作り手の思いが込められた真摯なものづくりから生み出されるたしかなクオリティを備えた時計は、スケールメリットを享受するメジャーブランドの時計にも決して引けを取らないことを物語っている。
現代の時計愛好家たちはSNSやコミュニティを通して、時計に関する情報を、そのよしあしをたやすく共有することができる。今や時計を愛する彼らを欺くことはそう簡単にはできない。たとえどんなに優れたマーケティング戦略があろうと、共感を呼ばないようなものは淘汰されることだろう。そして質・量ともに、作り手からの一方的な提案のもとで生み出される時計は、もはや時代を超えて受け入れられることは困難だ。それはインディペンデントブランドだけの話ではなく、すべての時計ブランドに言えることでもある。
Photographs by Yoshinori Eto







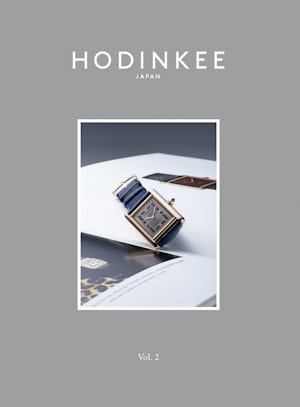





















話題の記事
大谷翔平選手がグランドセイコーのグローバルアンバサダーに就任
ベルナルド・レデラー&ラウル・パジェス ― いま世界が最も注目する独立時計師
グランドセイコー ヘリテージコレクション SBGA521 阪急うめだ本店限定モデル